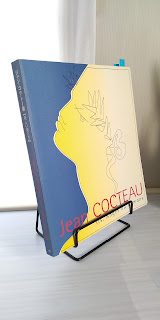[目次]
・おフランス文学とバナナのたたき売り
・人様の運、自分の運
・世界堂さんと朝日カルチャーセンターの思い出
・もっと自由に
おフランス文学とバナナのたたき売り
昨日は個人的にブームになっている「図書館にチラシがあった無料/廉価イベントに行ってみよう!」シリーズで、荻野アンナさんの講演会「本と私 読んで書いて60年」を聞いてきました。参加無料・自由席ですが事前申し込みが必要で、受付開始後まもなく満席になったそうです。自分は特にファンというわけではなくたまたま見つけただけなので、もしファンの方で入れなかった方がいらしたら申し訳ない。(^^;)でもお話から間接的に良い影響を受けてきました。
講演は荻野さんのご両親の出会いからご自身の現在までの生い立ちに、本好き・物書きになった経緯、持ちネタのラブレーのお話(これはやはり長め。「推し」ですもんね(笑))、影響を受けた文学作品の一節などを交えて進みました。
おなじみのダジャレをところどころに挟みつつも、訥々とした語り口。(原稿を読んでいらっしゃったのも一因でしょうか。でももともとこんな感じだったような?)OHP…じゃなくて今はなんていうんでしたっけ。あの資料をスクリーンに映すやつ。(今はデジタルで…やばいぞ商品名が思い出せない!(^^;))とにかくあれで紹介された文章は資料として配布もされて、知らなかったものが大半なので刺激になりました。絵画も資料で配布してくれれば良かったんだけどなあ…。『ガルガンチュア』や『パンタグリュエル』のクラシックな挿絵を紹介してくださったんです。これはお値打ちでした。(私には学校の世界史で出てきた「単語」程度のイメージしかなかったのに、ビジュアルが付いたんですから!)
ただ、芸風(?)が、この小見出しにしたようなギャップ芸——「恵まれた容姿と生い立ちを持つインテリ層の方が、"意外に庶民的/お調子者"な側面を無理に(というか実際そうなのだからじつは無理でもなんでもない)、自虐的に披露なさっている」——なので、ちょっぴり妬まれてしまうこともありそう。実際自分などは「(下層目線で)逆説的に片腹痛いわ☆」みたいな感覚もすこーし起こりました(私いやな奴ですね!(笑))。でもその場にいると「観客としてそれは大人げないぞ」という気分になって、実際お話にだんだん引き込まれていきました。そして「芸風」の一端は、「恵まれた部分から逆説的に派生する逆境」で身につけられた処世術かな……という感じにも見えてきました。
自著の売り込みをさりげなく織り込むのもかえって好感が持てましたし、引用された「良心のない知識は痴識」といった警句なども、素直に気持ちよくいただけました。横浜市の読書推進活動の一環としても沿った内容だったと思います。ただこういうのって「すでに本好き」の人が集まるものなので、ちょっと皮肉かもですが(笑)…こういう無料の地域のイベント、節約モードのインドア派には得難い刺激の場でありがたいです。
…じつは以前は「コミュニティなんたら」とか目に入るだけでも毛嫌いしていたのに(なんか書いててつくづくいやな奴だな私☆(^^;))、図書館にチラシのある地域イベントへの参加はえらい方向転換です。最近なぜか心理的氷解が起こっていろいろ楽しめるようになったので…。
「地域のなんたら」が苦手だったのは、たぶん以前目にしていたのは「子供」や「親子」、あるいは「リタイアした高齢者さん」などを想定した「参加者同士や主催者とのコミュニケーション込み」のイベントだったからかな、と思っています。最近そうでもないのがけっこうあるのに気づき、しかも講演はオンラインのものも。「見るだけ」「聞くだけ」なら気楽です♪
…脱線失礼しました!
講演後には「バナナのたたき売り」風の「自著のたたき売り」もありました。口上が面白かったです。「売るほどあるけど売れない」「(これを2冊買えば)娘に虫がつかない(著者が「虫がつかない歴60年」という——ご自身は「籍を入れなかっただけ」だと思いますがこういう言い方をされると親しみが(笑))」 ……などなど。語り口がもう少し流暢でいらしたらものすごく盛り上がりそうだなーと……講演も含めこれが少し残念でした。(まあ芸人さんではなくあくまで学者さんなので、そこまで求めるのが無理というもの☆)
たたき売りは座席の脇で行われて、見づらかったので途中であきらめて出てきましたが、舞台で演じられて見える状況だったらもう少し見ていたかったな…。単純に「見た目上品で美しい方」が「たたき売り」を演じているだけでもギャップが楽しいですから。(美しいのも芸のうち!) でも目の高さが同じでないと「たたき売り」の雰囲気は出ないですね。じつは正しい「たたき売り」なのでした。
…告白しますと、じつはご著書はちゃんと拝読したことがなくて、むかーし『世界古本探しの旅』っていう写真の多い共著本で寄稿部分と写真を目にしていたくらい。(これまた申し訳ないです(^^;))でも昔ときどきテレビで拝見した記憶はあって、美しい外見と「ラブレー」という発音のイメージ、断片的な予備知識はありました。生い立ちは知らなかったので、今回いろいろ納得しましたし、自分についても新たな視点を手に入れました。
人様の運、自分の運
お父様がアメリカ人、お母さまは日本人の画家。お母さまが装丁をした小説のゲラをアンナさんがたまたま読んで、編集者に感想を伝えたのがきっかけで書評を書くようになり、小説を書いて受賞までつながっていったことなどは……「ああ、やっぱりそういうつながりってあるんだなぁ……」と思いました。作家さんで「親が出版業界につながりを持っていた」方はけっこういらっしゃいますが、それだけでスタート地点が違う。これはもう妬みでも何でもなく事実ですね。
でもそれはたぶん、他の業界・職業でも同じですよね。(あら、書いて初めて気づいた。これが書き出すことの効用ですね☆)幼い頃自然に目にしていた物事や体験が「当たり前」の基準になる——だから子供の環境はできるだけ配慮してあげるべきなんですね。
作家の子供は、何かを書いて編集者に見てもらい出版してもらって、不安定な収入を得ることを特別なことだとは思わないでしょう。同じようにシェフの子供は、厨房で料理して人様に食べてもらって、不安定な収入を得ることを特別なことだとは思わないでしょう。サラリーマンの子供は、「学校を卒業したらどこかの会社に就職」して、毎月安定した収入を得ることを特別なことだとは思わないでしょう。いずれも心理的障壁が低くなるし、その分チャンスも増えます。
…そして親の路線に従っても、すべて成功する訳ではないのも多かれ少なかれ同じ。そこから先はご本人の資質や努力や環境と運なのでしょう。まあ運とまとめてしまえば努力できる能力もタイミングも運だし、出版業界も含めて昨今言われる「親ガチャ」から逃れてはいない、ということかなあ……。でも誰もが、それぞれに持っている「恵まれた部分」はあるはずです(運と逆説的なものも含めて)。というのは、ものごとの価値は「見方しだい」ですから。そして「その恵まれた部分の範囲」を超えてアウェーに出る自由がある(はず)、というのももちろん同じでしょう。
で、「自分の恵まれているところ」も考えてみました。…「ないことはない」、ことに気づきました。(笑)
世界堂さんと朝日カルチャーセンターの思い出
今回、間接的に良い影響を受けたと書きました。上記の「気づき」以外に2つあります。ひとつは、じつは講演を聞いている最中から、ぜんぜん関係ないのに「やっぱアナログで絵を描きたい。それも漫画以外のペン画!」との思いがふつふつと湧いてきまして。じつは昨年からの断捨離で、ペン軸とペン先を手放していたんです。というのも、最近はデジタルで描くので実質使わなくて、「子供の頃から使っていたから」というお守りみたいになっていたので。でも「ペンで描く感覚」をとにかく味わいたくて、買い直そうと決意。帰りに画材屋さんに行きました。(これはかねてからの予定で、じつは最近額装に興味が出ているので、マットや額縁が見たかったのです)
行ったのは横浜駅直結のルミネの8階にある世界堂さん。これまでは横浜の画材屋さんというと西口のToolsさんしか知らなくて、こちらはすごく縮小してしまったので(今の店舗になってからだいぶ経ちますが、自分が横浜駅を日常的に使っていた頃は上の方の階でもっと広かったのです)、他にないかなあと前日に検索して、初めて行ったお店です。最初は「8階なんてずいぶん上の階で行きにくいなぁ…」と思ってたんですが、行ってみたら朝日カルチャーセンターの横で。「ああ、ここにこれあったっけ!」と一気に記憶がよみがえりました。
余談の私事になりますが……実は昔ここで生け花を習っていたんです。20年くらい前でしょうか……勤めていた会社を辞めて、比較的余裕があった時期でした。(時間も退職金もあった)。この余裕は期間限定だとわかっていたので、独学でやっていた生け花をこの機会にきちんと習ってみよう、と思ったのでした。受講する前に流派について調べて、「生け花はもとをたどれば源流が一つで基本はどこも同じ」と知り、水曜日に開講していた草月流を選びました(もう少し古風なほうが好みではありましたが、帰りに映画館のレディースデーに行けると思って(笑))。いちおう名前をいただく辺りまで続けましたが、それが目標だったわけではなく、そこから先は講師になるための勉強になる、というタイミングでやめました。生けるのはひたすら楽しいのですが、自分が生けたいだけだったので…。生け花も「作品を作るより作り方を教えるほうが稼げる」ものの一つなので、自然な流れなのでしょうね。でも自分はだいたい人様にものを教えるような器ではありません。(笑)
閑話休題、当時はフロア全体がカルチャーセンターでしたが、その一角が画材屋さんになっていました。なるほど、アート系講座の受講者さんが自然に常連客になるわけですから、これは良い所に目をつけたなあ! …とにかくその世界堂さんでいろいろ物色して、ペン軸とスターター向けのペン先「画き味くらべ」セット、漫画ではなく絵を描きたいだけなので、気楽に小さく書けるように(あと、うまく描けたのを自宅で飾りやすいように)はがきサイズの用紙パック(ワトソン紙と厚いクラフト紙)、当初の目的だつたカット済の額装用マットを買って帰りました。ペン軸は丸ペンも匙タイプも付けられて、しかもペン先を付けたときに先端を覆ってくれるキャップがついている! 手に刺した経験が数えきれない身には目からウロコ! なんて素晴らしい進化!!!(笑)
もっと自由に
影響の2つ目は、「こんなにやりたいことをめいいっぱいやってる人がいるのに、自分は何を遠慮してるんだろう」…という気持ちが湧いたこと。上記の道具を買い直したのもその発露かもですが、ぶっちゃけ「売れるもの/売るためのもの」でなくともいいじゃないか、という天啓を得ました(この部分は荻野さんとは関係なく)。同人誌や個人出版なんて、普通の出版に比べたらなんでもありのはずなのに。なんだか自分の活動をすべて同人誌イベントに向けたものに「そぎ落とし」、すごく窮屈に考えてしまってました。別に発表することが前提でなくていいんだ、と。これはすごく自由になりました。絵を描くことが版下づくりになってしまい、発想も狭くなっていた。それに気づけただけでも、今回の講演会は実り多いものでした。
あ、あともう一つありました。「文章は簡潔に」が必ずしも常に正義ではないと思えた(ラブレーの冗漫な文体が肯定されていた)こと。今回あまり推敲で削らなかったのはそういうわけです。(笑)